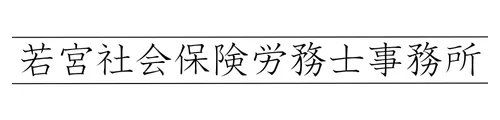自分に自信がない人へ、成功体験を得て自己効力感を高めよう

この記事の内容
あなたの自己効力感、高いですか?低いですか?
自己効力感とは、簡単に言えば、「自分ならやれるはずだ」という自信のようなものです。
自己効力感が高い人は、望む結果を得るために努力をする傾向にあります。
高い自己効力感は、困難な課題に取り組む際の原動力の一つとなり、成功の可能性を高めるのです。
一方、自己効力感が低い人は、物事をあっさりと諦めてしまう傾向にあります。
ということであれば、自己効力感は低いよりも高いに越したことはありません。
この記事では、そのような自己効力感を高めるために何が必要かについて解説しています。
自己効力感とは
自分ならできるという感覚
自己効力感とは、心理学者のバンデューラが提唱した概念です。
それは、
「ある課題に直面したときに、その課題を自分の力で効果的に処理できるという信念」
というようなものです。
結果を出すための2つの期待
また、バンデューラは、
私たちが行動して結果を出す際には2つの期待がある
としています。
その2つの期待とは「効力期待」と「結果期待」で、
この2つの期待が、自己効力感を考える際のキーとなります。
効力期待とは
効力期待とは、行動に対する期待です。
つまり、ある結果を得るために、自分がそのための行動を上手くできるかどうかという期待で、
「自分ならこの程度はできるだろう」という期待です。
結果期待とは
結果期待とは、自分が望む結果を出すために、このように行動すれば結果につながるだろうという期待です。
つまり、
「○○すれば、□□できるはずだ」という期待です。
重要なのは効力期待
私たちは、「○○すれば、□□できるはずだ」という結果期待を持っていたとしても、
「自分にはそのための行動を上手くできるはずだ」という効力期待を持っていなければ、
行動を起こすことができません。
そのため、より重要になるのは「効力期待」です。
効力期待は努力につながる
自己効力感とは、自分が効力期待を持っていると自覚したときに得られる自信のようなものです。
そして、「自分には上手くできるはずだ」という効力期待は努力につながり、
効力期待が高ければ高いほど、
困難に直面した際の踏ん張りがきくことになります。
効力期待と結果期待、その高低の組み合わせパターン
パターンは4つ
私たちの感情や行動は、
効力期待と結果期待の高低の組み合わせに影響を受けます。
高低の組み合わせとその影響は、
次の4つのパターンが考えられます。
私たちはどの組み合わせでどうなりやすいのか、
順に見ていきましょう。
効力期待も結果期待も高い場合
良い結果が得られるはずだという結果期待が高く、
そのために自分はうまく行動できるという効力期待も高い状態です。
このような場合、
私たちは
積極的に自信に満ちた行動をすることができます。
効力期待が高く、結果期待が低い場合
自分は上手く行動できるという自信はある(効力期待が高い)ものの、
それが望む結果につながりにくい(結果期待が低い)状態です。
このような場合、
私たちは
不満がたまりやすくなります。
効力期待が低く、結果期待が高い場合
望む結果を得たいと思う(結果期待が高い)ものの、
自分にはそのための能力がない・上手く行動することができないと感じている(効力期待が低い)状態です。
このような場合、
私たちは
劣等感を抱き、自分を卑下し、落胆することになります。
効力期待も結果期待も低い場合
上手く行動する自信がなく(効力期待が低い)、
良い結果を得ることもできないだろうと考える(結果期待が低い)状態です。
このような場合、
私たちは
無気力・無感動・無関心の状態となり、抑うつ状態になりやすくなります。
自己効力感を形成するために
自己効力感に影響する4つの要因
自己効力感を得たいとき、
あるいは誰かに自己効力感を得てもらいたいとき、
私たちはどうすればよいのでしょうか?
バンデューラは、自己効力感の形成に影響する要因として、次の4つをあげています。
- 行動遂行
- 代理経験
- 言語的説得
- 情動の喚起
最も効果的なのは行動遂行だとされていますが、
順に見ていきましょう。
行動遂行
行動遂行とは、成功体験を持つ、あるいは持たせることです。
実際に何か行動し(行動させて)、成功体験を得るようにします。
簡単なことで構いませんので、とにかく成功体験を得て、「できたこと」を強調します。
「何ができたのか」「どこが良かったのか」を評価し、自己効力感を高めていきます。
代理経験
代理経験とは、他人の経験から成功の情報を得ることです。
たとえば、
同じような境遇にある人のブログやSNSを見て、
- 自分もあのようにすれば成功できそうだ
- これなら自分も上手くやれそうだ
- この人ができたのだから自分もできるはずだ
と思うことがあります。
そのように他人が成功した経験をとおして、自己効力感を高めていきます。
言語的説得
言語的説得とは、行動ではなく言葉による説得です。
- 私(あなた)はやればできる
- 私(あなた)にやれないはずがない
- 私(あなた)はもともと優秀な人だ
というように言葉で説得したり励ましたりし、自己効力感を高めていきます。
子どもを「やればできる子」という言葉で励まして勉強するように導いていく方法は、これに該当するでしょう。
情動の喚起
情動の喚起とは、何かのきっかけで気持ちが喚起されることです
私たちは、
気持ちが安定してゆとりのあるときには、
期待を持ちやすくなり自己効力感が高まりやすくなります。
たとえば、
- 趣味でリフレッシュしたとき
- 好きな音楽を聴いたとき
- おもしろい映画を観たとき
自己効力感につながる気持ちが呼び起こされることがあります。
まずは気持ちを安定させること――
たしかに大切ですよね。
まとめ
気分が落ち込んでいるとき、
私たちの自己効力感は極度に低下しています。
それは、
効力期待も結果期待も低下した状態です。
そのような状態では、
あらゆる物事に対して
- 無気力
- 無感動
- 無関心
となってしまいます。
そこから脱却しようとする際、
この記事で紹介した
自己効力感の形成に影響する要因――
- 行動遂行
- 代理経験
- 言語的説得
- 情動の喚起
これらが役に立つのではないでしょうか。
参考リンク
🔗セルフエフィカシー:用語解説|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
この記事を書いた人
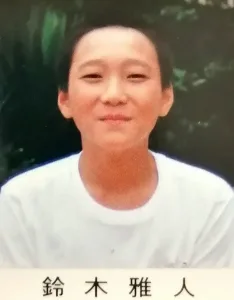
| 氏名 | 鈴木 雅人(すずき まさと) |
| 生年月日 | 1980年(昭和55年)4月1日 |
| 国家資格 | 社会保険労務士 第10230004号 精神保健福祉士 第26879号 |
| 座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |